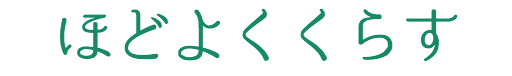ジビエとしても人気の高い鹿肉。
日本ではあまり出回っていませんが、ヨーロッパでは高級肉であり家畜として飼われている国もあるそう。
珍しい鹿肉を買ってみた、貰ったけどどうやって食べたらいい?という疑問に、猟師であり主婦でもある筆者がお答えします。
料理の専門家ではありませんが、簡単にできる家庭料理ですので参考になれば幸いです。
鹿肉の特徴
私は猟師さんからいただいた鹿肉が美味しかったことがきっかけで狩猟を始め、週に2,3度のペースで鹿肉を食べています。
鹿肉は『何をしても美味しい!』というお肉ではない、適した調理方法があるお肉であると感じています。
それは鹿肉には以下のような特徴があるからです。
- お肉の味や硬さに個体差がある
- 高温での調理は硬くなりやすい
- 普段食べているお肉に比べると脂の融点が高い
- 筋膜やスジが硬い
お肉の状態や個体、部位によって食べ方を変えるとより美味しく鹿肉を楽しめます。
鹿肉の下ごしらえ

買ったお肉や、いただいたお肉の状態によっては、下ごしらえが必要になります。
特に、筋や筋膜のついた状態のお肉を高温で焼いて調理するとスジが硬くなってしまい食べ難いです。(写真でいうと白い部分)
圧力鍋で煮込む場合はスジも食べられるようになりますが、焼き物の場合は取り除くことが望ましいです。
主婦猟師の鹿肉が美味しい基本のレシピ5つ
本記事では、比較的簡単な基本の調理方法を紹介します。
- 鹿肉のロースト
- 鹿肉の低温調理ユッケ
- 鹿肉のステーキ
- 鹿肉のシチュー
- 鹿肉の塩麹唐揚げ
①鹿肉のロースト

鹿肉のローストは高温で硬くなってしまう鹿肉を、最も美味しく食べられる調理法の1つです。
ソースはお好みで、わさび醤油やハニーマスタードソース、やきにくのタレなどで。
- 鹿肉の脂や筋をきれいに取り除き、下味に塩コショーをし10分ほどおく。出てきた水分は拭き取る。
- フライパンを熱しオリーブオイルを引き、お肉の表面に焼き目をつける。
- お肉に焼き目がついてきたらフライパンから取り出す
- 耐熱の保存袋(ジップロックなど)にお肉を入れる
- 大きめの鍋に湯を沸かす
- お湯が沸いたら火を止め、お肉の入った袋を入れ20分ほどおく(低温調理)
- 火の通り具合をみて好みのところで取り出す。
- 薄く切り盛りつけたら完成
もともとオーブンで焼く方法で作っていたのですが、時間もかかるし火の通り具合が難しく、ジップロックに入れてお湯につけておくサラダチキン方式で作っています。
お湯の調理でも難しいのは、やはり火の通し加減です。
これは使う鍋の熱伝導率や、もともとのお肉の温度、お肉のサイズなどによって変わります。
食べるときに切り分けますので、途中火の通りを確認するために切り目を入れても問題ありません。作りなれないうちはこまめに確認すると良いでしょう。
一番確実なのは低温調理器を使用することだと思います。
おすすめの部位:もも肉、背ロース
②鹿肉の低温調理ユッケ

低温調理ユッケは鹿肉のローストのアレンジレシピです。
鹿肉は赤身肉の味がしっかりするので、ユッケの味付けがとても合いますし、味付けの失敗の心配がありませんのでおすすめです。
- 鹿肉を耐熱の保存袋(ジップロックなど)に入れ、焼肉のたれを少量入れ下味をつける
- 大きめの鍋に湯を沸かす
- お湯が沸いたら火を止め、保存袋に入れた鹿肉を入れる
- 20分ほど蓋をして入れておく
- お肉を切って中がピンク色に火が通っていれば食べやすい大きさに切る
- 器に盛り付け、焼肉のたれ、ごま油、卵黄を乗せる
- お好みでネギ、白ごまなどをかけて出来上がり
おすすめの部位:もも肉、背ロース
③鹿肉のステーキ

鹿肉をステーキで食べる場合、高温で一気に中心部まで熱するとお肉が硬くなってしまうことが多いです。
焼き加減はミディアムレア~ミディアムくらいが理想。
あらかじめ筋の部分は取り除き、牛ステーキのようには大きく切りすぎず筋繊維を断ち切るようにお肉を切ると食べやすいです。
お好みのハーブと一緒に焼くのもオススメです。私はピンクペッパーで食べるのが好みです。
- お肉の筋を取り除く
- 硬さがきになる場合はフォークなどで刺して筋繊維を断つ
- フライパンを十分に熱しバター、もしくはオリーブオイルをひき、お好みの硬さに焼き上げる
- お好みのソースをかけてできあがり
おすすめの部位:もも肉、首肉、背ロース(特に仔鹿がおいしい)
④鹿肉のシチュー

鹿肉の煮込みは、旨味がスープに溶け出し味わい深い料理です。圧力鍋を使えば筋のある部位でも美味しく食べることができます。
お肉を大きいまま入れれば見た目も華やかなメインディッシュに。
味付けも市販のビーフシチューのルウを使用すれば簡単に美味しく出来上がります。
- 鹿肉を好みの大きさに切り圧力鍋に入れ、お肉が浸るくらいの水を入れて30分煮こむ
- たまねぎ、人参は一口大に切り、油をひき別鍋で炒める。
- 圧力鍋の鹿肉が箸で切れるくらいの硬さになっていたら、野菜を炒めていた鍋にお肉を移動し、一緒に炒める
- ビーフシチューのルウの説明書きのとおり、水の代わりに鹿肉の煮汁をいれる(煮汁のくさみが気になる場合は使用せず、新しくお水を入れる)
- ルウを入れ、煮込んでできあがり
凝った料理にしたい場合は赤ワイン煮込みなどもオススメです。
圧力鍋で煮た鹿肉は牛肉の赤身に風味が似ていますので、ビーフカレーの要領でカレーにするのも美味しいですよ。
ちなみに、圧力鍋ではなく普通の鍋で作ったことがありますが、3時間ほど煮ないとやわらかくなりませんでしたのであまりオススメしません^^;
おすすめの部位:前足、スネ肉など
⑤鹿肉の塩麹唐揚げ

我が家の鹿肉の塩麹唐揚げです。
鹿肉は高温での調理が硬くなりやすく、唐揚げとの相性はあまり良くありませんが塩麹に漬け込むだけでお肉がとても柔らかく仕上がります。
漬け時間はオスの成獣など硬さの気になる場合は1晩、メスや子鹿で柔らかい場合は3時間くらいでも柔らかくなります。
- 鹿肉は一口大に切り、塩麹につけこむ
- 鹿肉を食べやすいように切り(小さめ、かつ繊維が短くなるように切ると良い)、ついている塩麹は軽く落とす
- おろし生姜、おろしにんにくで味付けをし、片栗粉をまぶして180度に熱した油で揚げる
おすすめの部位:もも肉、内ロース
そのほかのアレンジレシピ
基本のレシピに加えよく作るアレンジメニューのレシピは別記事にまとめています。
鹿肉に飽きたから他に食べ方ない?と感じた方はこちらから。
鹿肉の調理にオススメの調理器具
鹿肉は一気に火入れをすると硬くなり、初めての調理はなかなか難しいものです。
我が家では美味しく無駄なく鹿肉を食べるために、いくつか調理器具を導入しました。
美味しい鹿肉を食べたい方は是非こちらもご覧ください。